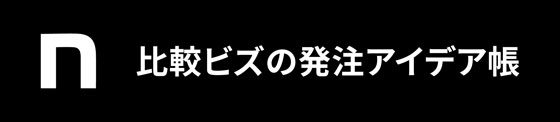青色申告で住民税は安くなる?住民税の計算方法や特別控除の条件も解説!
- 青色申告特別控除の条件とは?
- 住民税の計算方法は?
- 個人事業主が住民税に関して把握しておくべきポイントは?
青色申告特別控除が認められると課税所得を減らせるため、白色申告と比べて住民税を大幅に削減できます。しかし、青色申告特別控除を受けるためには、複数の条件を満たさなければいけません。
この記事では、住民税の計算方法や青色申告特別控除を受ける条件を解説します。最後まで読めば、個人事業主が把握しておくべき住民税のポイントもわかるでしょう。個人事業主の方や、個人事業主への転向を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
もしも今現在、
- 信頼できる税理士に依頼したい
- 自身の状況に合わせた税務アドバイスがほしい
- 税理士の費用相場がわからない
上記のようなお困りがありましたら、比較ビズへお気軽にご相談ください。比較ビズでは、複数の税理士・公認会計士に一括で見積もりができ、相場感や各社の特色を把握したうえで業者を選定できます。見積もりしたからといって、必ずしも契約する必要はありません。まずはお気軽にご利用ください。
兵庫県神戸市出身。趣味は筆跡診断・筆文字。神戸大学経済学部、甲南会計大学院卒業。2010年公認会計士試験論文試験合格後、上場会社経理部に所属し、固定資産・消費税を担当。その後、大手監査法人で会計監査、グループ会社で内部監査・人事に携わる。2020年4月から東京都品川区で個人事務所を開業し、会計システム導入支援・記帳代行に従事。2020年11月税理士登録。
青色申告により住民税額を削減できる
住民税は、個人事業主が得た前年の所得額に応じて納税額を算出します。青色申告によって特別控除が適用されると、最大65万円を控除した所得額で住民税を計算するため、大幅な節税効果が見込める仕組みです。
たとえば500万円の所得を得ている個人事業主の場合、特別控除を認められると総所得は65万円を引いた435万円となります。住民税の税率は一般的に10%であるため、65万円の10%に該当する65,000円が節税可能です。
住民税とは
住民税とは、各地域に住む人々が都道府県や市町村に支払う税金です。住民から支払われた税金は、水道・福祉・ゴミ処理など、さまざまな行政サービスの維持管理費に充てられます。
住民税の納税対象地域は、1月1日時点で住んでいる都道府県や市区町村です。個人事業主の住民税は「個人住民税」に該当し、確定申告の内容に基づいて納税額が決められます。 個人事業主の住民税額は各自治体が計算するため、改めて手続きを行う必要はありません。
住民税の計算方法
個人事業主の住民税は、以下の2つによって納税額が算出されます。
- 均等割
- 所得割
所得割は前年の所得額をもとに算出しているため、毎年変動するのが特徴です。
均等割
均等割は、所得金額に関わらず、すべての住民に対して平等に課せられる課税です。多くの自治体では、都道府県民税が1,500円、市区町村民税が3,500円、合計5,000円に均等割を設定しています。
一部の地域では独自の税率を採用して税額が異なる可能性もあるため、自治体のホームページを確認しましょう。
所得割
所得割は前年の所得によって算出されるため、個人事業主によって納税額は異なります。以下の計算式によって、納税額を算出する形式です。
- (前年の所得-所得控除)×(税率)-(税額控除)
税率は都道府県民税が4%、市区町村民税が6%を合算した10%が一般的です。自治体によっては独自の税率を採用している場合があるため、注意してください。
たとえば前年の所得が600万円、所得控除が100万円、税額控除が30万円である場合、所得割の計算は以下のとおりです。
- (600万円-100万円)×0.1-30万円 = 20万円
所得控除は社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除などが対象です。税額控除は住宅ローン控除や配当控除などが適用されます。
青色申告特別控除を受けるための6つの条件
青色申告特別控除を受けるための条件は、以下の6つです。
- 事業所得または不動産所得がある
- 複式簿記で記帳をしている
- 貸借対照表と損益計算表を作成している
- 期限内に確定申告を済ませている
- 開業届と青色申告承認申請書を提出している
- e-taxによる申告または電子帳簿保存を実施している
1. 事業所得または不動産所得がある
青色申告特別控除を受けられるのは、事業所得または不動産所得を得ている個人事業主のみです。国税庁が定めている事業所得を、以下にまとめました。
- 農業
- 漁業
- 製造業
- 卸売業
- 小売業
- サービス業
- その他事業
その他事業に該当するのは、ライターやデザイナー、エンジニアなどです。事業収入から経費を引いた年間所得額が48万円を超える方が、確定申告の対象となります。
マンションやアパート経営で不動産所得を得ている場合、不動産貸付けが事業として行われていると認められなければいけません。貸間やアパートなどの場合、独立した部屋数が10室以上必要です。独立家屋の貸付けの場合、5棟以上が必要となります。
参照:国税庁
2. 複式簿記で記帳をしている
簿記とは、事業運営による資産の増減や取引内容を記録することです。簿記には複式簿記と単式簿記の2種類があり、青色申告特別控除を受けるには複式簿記で帳簿付けをする必要があります。
複式簿記は、取引内容を複数の勘定科目で記帳する方法です。一例として、取引先に総額50万円分商品を販売し、現金で報酬を得た場合の記帳内容を以下にまとめました。
| 日付 | 借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/1 | 現金 | 500,000円 | 売上 | 500,000円 | 取引先Aに商品Aを売り上げた |
記帳内容をもとに、 貸借対照表と損益計算書を作成します。
3. 貸借対照表と損益計算書を作成している
青色申告特別控除を受けるためには、確定申告書に加えて貸借対照表と損益計算書の添付が必要です。いずれの書類も、個人の資産や企業の経営状況を把握するうえで重要な書類の財務諸表に該当します。
貸借対照表とは、特定のタイミングにおける財政状況を示す書類です。現金・売掛金・買掛金など、資産や負債を勘定科目別に記載し、事業の安定性や負債の支払能力を可視化します。
損益計算書とは、1年間の収益や事業の成長度を示す書類です。収益・費用・純利益を記載し「前年と比べてどの程度売上や利益が伸びたのか」を明確にします。 クラウド型会計ソフトを導入すると、比較的スムーズに貸借対照表と損益計算書の作成が可能です。
4. 期限内に確定申告を済ませている
確定申告の期限は例年2月16日〜3月15日と定められており、青色申告特別控除を受けるためには期限内での申告が前提です。仮に3月16日以降に手続きした場合、最大でも10万円しか特別控除が適用されません。ペナルティとして、無申告加算税や延滞税の支払い義務も発生します。
無申告加算税が発生すると、納税額に応じて以下の割合を加算した金額の納税が必要です。
| 50万円以下 | 50万~300万円まで | 300万円超 |
|---|---|---|
| 15% | 20% | 25% |
参照:国税庁
延滞税は、納付期限翌日から2カ月以内に申告した場合は納税額の7.3%、2カ月を超えた場合は14.6%に該当する額が加算されます。必要以上に税金を支払うことになるため、確定申告は期限内に済ませましょう。
参照:国税庁
無申告加算税は、期限内に確定申告を済ませなかった場合に発生する追徴課税です。税務署から指摘を受ける前に確定申告を済ませると、税率が5%まで減額されます。延滞税は、期限までに税金を納めなかった場合に発生する追徴課税です。
5. 開業届と青色申告承認申請書を提出している
個人事業主になったばかりの場合、青色申告を行うためには開業届と青色申告承認申請書の提出が必要です。開業届のフォーマットは、国税庁のホームページまたは税務署の窓口から入手できます。
1度に手続きを済ませるためにも、マイナンバーカードや運転免許証、印鑑を持参し、税務署で開業届を提出しましょう。開業届の提出期限は事業開始から1カ月以内です。期限を過ぎてから提出してもペナルティは発生しませんが、青色申告で申請できるのは翌年からになります。
青色申告承認申請書も、開業届と同じ方法でフォーマットの入手が可能です。提出期限は事業開始時期によって変動しますが、基本的に3月15日までに提出しなければなりません。
6. e-Taxによる申告または電子帳簿保存を実施している
上記5つの条件を満たすと青色申告特別控除が適用されて住民税が軽減されますが、最大55万円までしか控除されません。e-Taxまたは電子帳簿保存を実施すると、65万円の控除が受けられます。
e-Taxの利用には、マイナンバーカードや利用者識別番号を取得しなければなりません。 電子帳簿保存の場合は、仕訳帳や総勘定元帳など、各帳簿が「優良な電子帳簿保存」と呼ばれる要件を満たす必要があります。あわせて3月15日までに、以下の届出書を税務署に提出してください。
国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の 青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書
個人事業主が住民税に関して把握しておくべき4つのポイント
個人事業主が住民税に関して把握しておくべきポイントは、以下の4つです。
- 決定通知書が届いた後に自分で納付する
- 住民税は経費として計上できない
- クラウド型会計ソフトを導入する
- 税理士に相談する
1. 決定通知書が届いた後に自分で納付する
住民税の額は、確定申告の内容をもとに各自治体が納税額を計算するため、自身で計算をする必要はありません。計算が終わった後、納税額を記載した決定通知書に加え、4回分の納付書が個人事業主に発送されます。
決定通知書が届くのは6月頃です。個人事業主は会社員と異なり、住民税を自ら納付しなければなりません。期限内に納付しないと催促状が届き、最悪の場合は延滞税の支払い義務が生じます。
納付遅れの発生を避けるため、住民税の決定通知書が届いたら大切に保管し、スケジュール管理を徹底しましょう。
2. 住民税は経費として計上できない
住民税は事業運営に関係ない支出のため、経費として計上できません。健康保険料や国民年金など、社会保険料も経費として扱えませんが、所得からの控除が認められています。個人事業主が経費として計上可能な主な税金を以下にまとめました。
- 事業用の車両に関する税金(自動車税・自動車取得税・自動車重量税)
- 印紙税(収入印紙)
- 個人事業税
- 事業用の土地建物に関する税金(固定資産税・不動産取得税・登録免許税)
- 消費税
事業に関連している場合は、税金を経費として扱える場合があります。住民税をはじめ経費にできない税金を仕訳する場合は、事業主貸を勘定科目で選択してください。
| 日付 | 借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/1 | 事業主貸 | 30,000円 | 普通預金 | 30,000円 | 住民税納付 |
3. クラウド型会計ソフトを導入する
普段の帳簿付けや確定申告の手続きをスムーズに進めるために、クラウド型会計ソフトの導入もおすすめです。ユーザーインターフェースに優れており、簿記の知識がない方でも直観的に利用できます。
複式簿記での記帳に必要な作業は日付や取引金額の入力、勘定科目を選択するだけです。インターネットバンキングやクレジットカードとも連携しており、取引データを自動で取り込めます。
画面内容に沿って必要な情報を入力していくと、確定申告書や決算書も作成可能です。月額料金も数千円台に設定されているソフトが多く、予算の確保が難しい方も十分導入を検討できるでしょう。
4. 税理士に相談する
本業が忙しく確定申告に必要な書類作成に十分な時間を割けない方は、税理士に依頼するのも1つの選択肢です。豊富なノウハウと知識を持つ税理士に依頼すると、正確な書類作成が期待できるため、青色申告特別控除を受けられる確率が高まります。
スポットでの書類作成代行サービスを提供する税理士事務所も多く、必ずしも顧問契約を締結する必要はありません。資金調達の方法や起業支援、海外進出など、さまざまな内容に関して相談できる魅力もあります。
注意点は補助金の手続き代行や融資対策など、税理士によって得意分野が異なることです。確定申告の書類作成対応可否も含め、得意分野や実績を確認しましょう。
まとめ
青色申告特別控除を受けられると所得額が最大65万円控除され、住民税も65,000円安くなります。青色申告特別控除を受けるためには、複式簿記での帳簿や財務諸表の作成など、さまざまな条件を満たさなければなりません。
確定申告の手続きをスムーズに進めるには、税理士に相談するのがおすすめです。豊富な実務経験や知識を持っており、確定申告書類の正確な仕上がりが望めます。
比較ビズには、確定申告に強い税理士が数多く在籍しています。2分程度の入力で、全国の税理士事務所を比較しながら選択可能です。税理士事務所に依頼し、確定申告の負担を軽減したい方はぜひご利用ください。
兵庫県神戸市出身。趣味は筆跡診断・筆文字。神戸大学経済学部、甲南会計大学院卒業。2010年公認会計士試験論文試験合格後、上場会社経理部に所属し、固定資産・消費税を担当。その後、大手監査法人で会計監査、グループ会社で内部監査・人事に携わる。2020年4月から東京都品川区で個人事務所を開業し、会計システム導入支援・記帳代行に従事。2020年11月税理士登録。
当記事で見てきたように、青色申告特別控除は所得税だけでなく住民税も少なくすることができます。そのため、青色申告制度を利用するかどうか検討する場合には、所得税への影響だけでなく、住民税への影響も考慮して検討するといいでしょう。
青色申告制度を利用した場合の所得税や住民税への減少額と、複式簿記に対応するための会計ソフトや記帳代行、税理士に税務顧問を依頼することで発生する費用を比較すると同時に、自身で対応する場合の手間や費やす時間を天秤にかけ、青色申告制度を利用するかどうか判断することをお勧めします。
比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。
もしも今現在、
- 信頼できる税理士に依頼したい
- 自身の状況に合わせた税務アドバイスがほしい
- 税理士の費用相場がわからない
上記のようなお困りがありましたら、比較ビズへお気軽にご相談ください。比較ビズでは、複数の税理士・公認会計士に一括で見積もりができ、相場感や各社の特色を把握したうえで業者を選定できます。見積もりしたからといって、必ずしも契約する必要はありません。まずはお気軽にご利用ください。
確定申告に関連する記事
-
2025年12月02日確定申告マイナンバーで副業がバレる?勤務先にバレない3つの対策を解説
-
2025年12月02日確定申告株式売却の確定申告が必要なパターンは?確定申告に必要な書類や手順も確認
-
2025年12月02日確定申告確定申告を行うメリットとは?確定申告が必要なパターンや申告の流れも確認
-
2025年12月02日確定申告ウーバーイーツで確定申告すると会社にバレる?確定申告が必要な条件とやり方を …
-
2025年12月02日確定申告水商売の確定申告で経費にできる費用は?節税する方法やメリット2つ
-
2025年12月02日確定申告専業主婦の一時所得は確定申告が必要?保険金や年金の基礎控除・配偶者控除