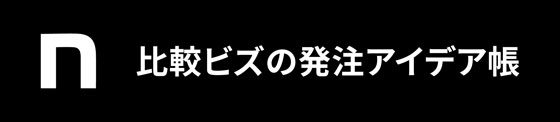ビジネスモデル特許とは?取得のメリット・デメリットや重要な審査要件について解説
- ビジネスモデル特許とは?
- 特許を取るべきかわからない
- 特許として認定されるかどう判断する?
「ビジネスモデル特許とは何か知りたい」「特許を取るべきかわからない」とお悩みの方必見。ビジネスモデル特許とは、ICTを活用したビジネス関連発明に関する特許のことで、取得することで事業実現において重要な技術を独占できます。
この記事では、ビジネスモデル特許取得のメリット・デメリットや取得における重要な審査要件、注意点について解説。記事を読み終わった頃には、ビジネスモデル特許を取得するべきか判断できるようになるでしょう。
もしも今現在、
- どの弁理士に依頼したらいいかわからない
- 見積もり金額を安く抑えたい
- 特許法や特許審査の手続きに関するサポートがほしい
上記のようなお困りがありましたら、比較ビズへお気軽にご相談ください。比較ビズでは、複数の弁理士に一括で見積もりができ、相場感や各弁理士の特色を把握したうえで業者を選定できます。見積もりしたからといって、必ずしも契約する必要はありません。まずはお気軽にご利用ください。
関西学院大学商学部出身。2007年12月弁理士登録。1999年より大阪市内の特許事務所にて知財業務の経験を積み、2018年4月弁護士法人英明法律事務所へ合流し、所内に知的財産権を専門に扱う部門を設立した。特許・実用新案(機械等の分野など)・意匠・商標の権利化業務に従事する。クライアントとのコミュニケーションを通じて適切な権利取得を心掛ける。
ビジネスモデル特許とは
「ビジネスモデル特許」という単語は、特許の分野において正式に存在する言葉ではなく、一般的に普及している通称です。特許庁では、ICT(情報通信技術)を利用して実現されたビジネス方法の発明のことを「ビジネス関連発明」と呼んでいます。
ビジネス関連発明は、ビジネス方法とICTをかけあわせたもので、コンピュータソフトウェア関連発明に含まれるものとされています。ビジネスモデル特許とは、ICTを利用して実現されたビジネス関連発明に関する特許であるといえます。
取得するべきかの判断材料は3つ
ビジネスモデル特許を取得するべきか判断するためには、以下の3つの観点から対象の技術について考える必要があります。
- 取得のメリットの恩恵をどれくらい受けるか
- 取得のデメリットの影響はどれだけあるか
- 特許取得のための要件をクリアしているか
これからビジネスモデル取得のメリット・デメリットと、特許を取得するための重要な要件について解説しますので、ぜひ参考にしてください。
ビジネスモデル特許取得のメリット
ビジネスモデル特許の取得で得られるメリットは、以下の3つです。
- 競合他社への優位性を確立できる
- 顧客や投資家へのアピールになる
- 助成金を受け取れる
1. 競合他社への優位性を確立できる
ビジネスモデル特許が取得できれば、他社への優位性を確立してビジネスを展開できます。事業の実現における重要な技術を独占できるため、競合他社は同じ技術を用いたビジネスを行えません。
特許を取得できれば、出願日から20年間は権利を維持できます。サービスのクオリティやスピード、効率性における品質の差が生まれ、収益性や安定性で競争率を高めることができるでしょう。
2. 顧客や投資家へのアピールになる
ビジネスモデル特許の取得は、顧客や投資家へのよいアピールとなります。独創的な商品やサービスであるという認定を受けることで、信頼感や安心感が生まれるためです。
実際に特許を取得すると「特許第〇〇号取得」と表示されるようになります。顧客への宣伝効果が高まり、投資家の興味を引くことにもつながるでしょう。
3. 助成金を受け取れる
ビジネスモデル特許を申請する際、自治体の助成金を受けとれる場合があります。たとえば東京都の「特許調査費用助成事業」は、特許の調査時に発生する費用の一部を負担する助成金制度です。
| 助成率 | 2分の1以内 |
|---|---|
| 助成限度額 | 100万円 |
| 助成対象経費 | ・開発戦略策定費用 ・特許出願戦略策定費用 ・継続的なウォッチングに要する費用 ・侵害予防に要する調査費用 |
ビジネスモデル特許を取得できれば事業を有利に進められますが、特許出願には多額の費用を負担しなくてはなりません。ビジネスモデル特許を出願する際は、地方自治体の助成金制度を調べ、積極的に利用しましょう。
ビジネスモデル特許取得のデメリット
ビジネスモデル特許を取得するうえでのデメリットは、以下の3つです。
- 発明の詳細が公開される
- コストがかかる
- 登録まで時間がかかる
1. 発明の詳細が公開される
すべての特許出願は、出願日から1年半経過後に出願内容の詳細が公開されます。特許を取得したビジネスモデルの内容をもとに、他社がさらに優れたサービスを開発する可能性があります。
ビジネスモデル特許権者には一定期間の独占排他権が与えられますが、他社にも詳細が明らかになることは避けられません。ビジネスモデル特許の取得を検討している場合は、競合他社に詳細が明らかになっても問題のないよう事業戦略を立てましょう。
2. コストがかかる
ビジネスモデル特許を取得するには、出願料、出願審査請求、特許印紙料、特許料などの費用がかかります。自分で手続きをする場合は総額で169,800円以上、特許事務所(弁理士事務所)に依頼する場合の目安は71万円〜98万円です。
【自分で手続きする場合】
| 特許出願にかかる特許印紙 | 14,000円 |
|---|---|
| 出願審査請求にかかる特許印紙 | 138,000円+(4,000円×請求項の数) |
| 承認された場合の特許料(3年分) | 12,900円+(900円×請求項の数) |
【特許事務所(弁理士事務所)に依頼する場合】
| ビジネスモデル特許の出願 | 35万円〜45万円 |
|---|---|
| 出願審査請求 | 16万円〜19万円 |
| 拒絶理由通知の対処 | 10万円〜18万円 |
| ビジネスモデル特許取得時の成功報酬 | 10万円〜16万円 |
ビジネスモデル特許を取得することで他社への優位性を確立できるとはいえ、10万円〜100万円の出費は小さくありません。自社にとって特許の取得はコストに見合う価値があるのか、慎重に検討しましょう。
3. 登録まで時間がかかる
特許の出願から審査結果の通知が届くまで、一般的には1年〜1年半の期間がかかります。出願から取得までに4年〜5年の期間がかかったケースもあります。ビジネスモデル特許を取得する際には、時間がかかる想定で事業・サービスの計画を立てなくてはなりません。
ビジネスモデル特許取得のための重要な3要件
ビジネスモデル特許において、以下の3点は特許取得の判定をわける重要な審査要件です。通常の特許出願と同様に新規性や進歩性、発明該当性の高さが認定のポイントです。
- 発明であること
- 新規性があること
- 進歩性があること
1. 発明であること
ビジネスモデル特許における審査では、対象の技術の発明該当性が特に注視されます。特許法において「発明」は以下のとおりに定義されています。
この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
引用:e-GOV 法令検索
「自然法則」とは、万有引力の法則やニュートンの運動の法則など、人間がつくった規則や経済法則と区別されるものです。ビジネスモデル自体は「発明」に該当しないため、ビジネスモデルに「自然法則を利用した技術的思想の創作」にあたるICTを結びつける必要があります。
2. 新規性があること
従来の技術と比較し、自社の発明がより新しい内容であると認められる必要があります。日本の特許法では、特許が出願された時点(◯年◯月◯日◯時◯分)を基準に新規性が判断されます。
たとえ自社が初めて開発した技術であっても、すでにサービスが提供されていて世間に知られている場合、新規性は認められません。サービスの公開前に出願することが必要となるため、注意しましょう。
3. 進歩性があること
当該分野の人間から見て容易に思いつくもの・すでに特許が認められている内容を少し変更しただけのものは、特許と認められません。特許法における進歩性への言及箇所は以下のとおりです。
特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
引用:e-GOV 法令検索
進歩性は、以下の基準から判断されます。自身の考えた技術に進歩性があるか不安な場合は、特許庁の特許実用新案審査基準を確認しましょう。
| 進歩性が認められるケース | 既存のシステムを転用するだけではなく、新しい何かを創出していたり、独自で技術的な工夫を凝らしていたりする場合 |
|---|---|
| 進歩性が認められないケース | 既存のシステムを転用する・既存の手作業を自動化するなど、既存のものに少し手を加えただけの場合 |
ビジネスモデル特許の取得事例3選
ICTを利用して実現されたビジネスモデルとして、過去に特許を取得した事例を3つ紹介します。
- オープンマーケット社のショッピングカート
- Amazon.com社のワンクリック
- 凸版印刷株式会社のマピオン
オープンマーケット社のショッピングカート
参照:Amazon
オープンマーケット社のショッピングカートは、オンラインショッピングの決済の手続きに関する特許です。カート内に異なるショップの商品が混ざっていても決済手続きが1回で済み、ユーザーの手間を大幅に軽減しました。
Amazon.com社のワンクリック
参照:Amazon
ワンクリックは2回目以降の注文の際に購入ボタンをクリックすると、自動でユーザー情報を割り出して決済や発送準備の処理を行う仕組みです。Amazon.com社のワンクリックシステムによって、ユーザーが個人情報を入力する機会は初回購入時のみとなりました。
凸版印刷株式会社のマピオン
参照:Mapion
凸版印刷株式会社のマピオンは、インターネットのホームページ上の地図に企業や店舗などの広告を表示します。地図上にあるレストランや店舗などの画像アイコンをクリックすると、店名や電話番号、住所、メニュー、広告メッセージなどの情報が閲覧できます。
ビジネスモデル特許取得の流れ
ビジネスモデル特許を取得する際の流れは、以下のとおり大きく3つにわけられます。
- 特許を出願する
- 出願審査請求を払う
- 特許査定が届いたら特許料を支払う
1. 特許を出願する
特許出願書類の様式をダウンロードし、書き方ガイドを参照しながら記入します。出願に必要な書類のテンプレートは、知的財産相談・支援ポータルサイトよりダウンロードできます。
郵便局や特許庁で14,000円の特許印紙を購入し、特許出願書類の指定された場所へ貼り付けましょう。用意した書類は特許庁の窓口に直接持参するか、郵送で提出します。
2. 出願審査請求を払う
特許を出願しただけでは審査は始まらず、別に出願審査請求を行う必要があります。出願審査請求は特許出願から3年以内と期限が定められているため注意しましょう。
出願審査請求を行った後は、審査結果がわかるまで1年ほど待ちます。特許取得を急いでいる場合には早期審査・早期審理制度を利用しましょう。審査にかかる時間を3〜4カ月ほどに短縮可能です。
3. 特許査定が届いたら特許料を支払う
ビジネスモデル特許が認められ「特許査定」が届いたら、30日以内に特許料を支払わなければなりません。その後、特許の取得までに、特許の設定登録、特許原簿の作成、特許証の発行などの手続きがあります。
特許査定を受けた発明は、設定登録された日をもって特許権が発生します。特許査定が届いても、特許料を支払わない限りビジネスモデル特許を取得できないため注意が必要です。
ビジネスモデル特許取得で注意すべき点
ビジネスモデル特許を取得する際は、以下の3点に注意する必要があります。
特許が認められない場合がある
特許が認められず「拒絶理由通知」が届く場合があります。その場合、60日以内に意見書もしくは手続補正書を提出して再審査を申請しましょう。再審査の結果、先の拒絶理由が解消されたと判断されると、特許の登録手続きができます。
| 意見書 | 拒絶理由の異議を述べ、特許出願の妥当性を主張する。たとえば拒絶理由に「新規性を有しない」旨の記載があった場合には、発明の新規性を説明する。 |
|---|---|
| 手続補正書 | 発明の内容を一部変更することを申請する。 |
再審査を受けても特許が認められない場合、拒絶理由通知もしくは拒絶査定が届きます。拒絶査定は、特許を認めないという特許庁の審査官による最終判断です。拒絶査定に対して不服がある場合、拒絶査定不服審判の請求が可能です。
ビジネスモデル特許の海外での有用性
ビジネスモデル特許をはじめとした特許権は、特許を取得した国でのみ認められるため海外では無効です。海外でも特許を取得したい場合は、その国の特許庁にあたる場所で手続きを行わなくてはなりません。
海外での特許取得は、日本での取得よりも複雑です。個人でできる範囲を超えているため、海外での特許取得は特許事務所に相談することをおすすめします。
ビジネスモデル特許取得の難易度
ビジネスモデル特許の取得はさほど難しくありません。特許庁によると、2010年〜2017年の特許査定率(出願のうち特許として認められたものの割合)は65%〜74%で推移しています。
参照:特許庁
ただし、特許査定を受けるには、ビジネスモデル特許の性質や審査要件に対する高度な知識が必要です。「プロ(特許事務所)に依頼する場合、ビジネスモデル特許の取得の難易度が下がる」といえます。
まとめ
ビジネスモデル特許を取得する際は、取得におけるメリットやデメリットを踏まえ慎重に検討する必要があります。専門性の高い内容を理解する必要があるため、特許の取得を考えている方には特許出願に精通する特許事務所(弁理士)に依頼することがおすすめです。
ビジネスモデル特許の出願を依頼できる弁理士をお探しの方は「比較ビズ」をご活用ください。比較ビズには多くの実績豊富な弁理士が登録しており、2分程度の入力で簡単に一括見積もりが可能です。
関西学院大学商学部出身。2007年12月弁理士登録。1999年より大阪市内の特許事務所にて知財業務の経験を積み、2018年4月弁護士法人英明法律事務所へ合流し、所内に知的財産権を専門に扱う部門を設立した。特許・実用新案(機械等の分野など)・意匠・商標の権利化業務に従事する。クライアントとのコミュニケーションを通じて適切な権利取得を心掛ける。
増加の理由は、IoTやAIといった技術の革新的進歩を背景に、審査の基準が安定してきたことに伴う特許査定率の向上が要因の一つであろうと思われます。2000年当時の特許査定率は10%前後であったものが年々上昇し、近年では他分野同様65%〜70%で推移するようになってきました。
今後もこの傾向は続くものと思われます。ビジネスに関する新しい提供方法を思いついたときには、実施の可否や権利化の見通しなど、一度専門家へご相談頂くことをお勧めします。
比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。
もしも今現在、
- どの弁理士に依頼したらいいかわからない
- 見積もり金額を安く抑えたい
- 特許法や特許審査の手続きに関するサポートがほしい
上記のようなお困りがありましたら、比較ビズへお気軽にご相談ください。比較ビズでは、複数の弁理士に一括で見積もりができ、相場感や各弁理士の特色を把握したうえで業者を選定できます。見積もりしたからといって、必ずしも契約する必要はありません。まずはお気軽にご利用ください。