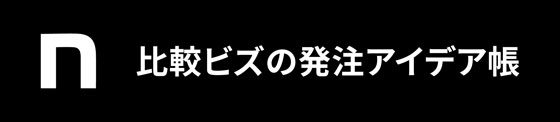ホームページの償却期間は、3年または5年です。ホームページは「複写して販売するための原本」や「研究開発用途のもの」に該当しないとされるため、5年間での償却が適用されやすいです。
たとえば、作成費用が10万円で、ホームページの有用寿命が5年とされる場合、年間2万円ずつ償却できます。会計基準や税法などが影響するため、具体的な償却年数は会計士や税理士に相談することがおすすめです。
ホームページ作成の勘定科目を分かりやすく紹介!経費計上の注意点3つや節税方法を解説
- ホームページ作成の勘定科目は?
- ホームページ作成時の経費を計上する注意点は?
- ホームページ作成時にできる節税方法は?
「ホームページ作成費用を経費にしたいが、勘定科目がわからない…」という方必見!
この記事では、ホームページ作成費用の勘定科目を適切に仕訳したい方に向けて、ホームページ作成の勘定科目を紹介。ホームページ作成時の経費を計上する注意点も解説します。
ホームページ作成費の適切な仕分けには正確な記帳が必須ですが、税理士や会計士に依頼することで仕訳や税務処理がスムーズになり、時間を節約できます。ホームページ作成時にできる節税方法も紹介しているので、副業や新規事業でホームページを立ち上げる方もぜひ参考にしてください。
もしも今現在、
- どの税理士に依頼したらいいかわからない
- 業界知識や実績が豊富な税理士に依頼したい
- 費用相場がわからず適正価格か不安
上記のようなお困りがありましたら、比較ビズへお気軽にご相談ください。比較ビズでは、複数の税理士・公認会計士に一括で見積もりができ、相場感や各社の特色を把握したうえで業者を選定できます。見積もりしたからといって、必ずしも契約する必要はありません。まずはお気軽にご利用ください。
ホームページ作成の勘定科目は「広告宣伝費」が一般的!
ホームページ作成費用の勘定科目は「広告宣伝費」が一般的です。特に、企業のPRや集客を目的としたコーポレートサイトやランディングページ(LP)などは、広告宣伝費として処理されることが多いです。
ホームページ作成時に広告宣伝費になる経費一覧
ホームページ作成時に広告宣伝費になる経費は、以下のとおりです。
| 開発費用 | ・ホームページの設計や開発、コーディング、デザインの費用 ・開発作業に関連する給与や外部委託費、ソフトウェアライセンス料も含む |
|---|---|
| デザイン費用 | ・ホームページのデザインやビジュアル要素の制作費用 ・ロゴデザインやイメージ画像、アイコンの制作費用も含む |
| ホスティング費用 | ・Webホスティングやドメイン料金の費用 ・サーバーの維持費やドメインの更新費用も含む |
| 広告・マーケティング費用 | ・知名度向上や集客のために行う広告やマーケティング活動費用 ・オンライン広告やSNSプロモーション、SEO対策も含む |
| 保守・運用費用 | ・ホームページの定期的な更新や修正、セキュリティ対策の費用 ・コンテンツの更新作業やバックアップの実施費用も含む |
| 研修・教育費用 | ・ホームページ運用に関わるスタッフの研修や教育費用 ・Webデザインやプログラミング言語のトレーニング費用も含む |
| 著作権料 | ・画像やテキスト、音楽などの著作権の取得費用 ・他者の著作物を利用時にかかる費用も含む |
ホームページ制作費のうち、広告宣伝目的の部分は「広告宣伝費」として計上しましょう。広告宣伝目的以外の部分(システム開発やドメイン・サーバー費用など)は「ソフトウェア」や「通信費」として適切に振り分けることが一般的です。
ホームページ作成時の経費を計上する注意点3つ
ここからは、ホームページ作成時の経費を計上する注意点を3つ紹介します。
- 資産計上か経費計上かを見極める
- 勘定科目の選定を適切に行う
- 運用費と作成費を区別する
1. 資産計上か経費計上かを見極める
ホームページ作成費用は、資産計上(無形固定資産)と経費計上のどちらになるかを慎重に判断する必要があります。ECサイトや予約システムなどの独自機能を持つホームページは、長期間にわたり企業の資産としての価値があります。
資産としての価値がある場合は資産計上となり、減価償却(5年)が必要です。一方、企業PRや集客目的のコーポレートサイトやランディングページは、広告宣伝費として即時経費計上できるため、税務上の処理がシンプルです。
2. 勘定科目の選定を適切に行う
ホームページ作成費用は、適切な勘定科目を選びましょう。一般的な企業サイトや販促目的のサイトは広告宣伝費として計上しますが、制作を外部の業者に委託した場合は外注費として処理することがあります。
ドメインやサーバーの維持費用は通信費、ホームページの軽微な修正や改修費用は修繕費として計上できます。それぞれの経費の特性を考慮し、誤った勘定科目で処理しないように注意しましょう。
3. 運用費と作成費を区別する
ホームページ作成に関する費用は、初期制作費と運用費を明確に区別することが重要です。作成時に発生するデザイン費やコーディング費用は作成費として計上し、広告宣伝費や外注費に分類されます。
サーバー維持費、ドメイン更新費用、記事更新費用、SEO対策費用などは運用費に該当し、通信費や広告宣伝費として処理しましょう。作成費と運用費を混同すると、税務上の処理が複雑になるため、適切に分類することが必要です。
ホームページ作成時にできる節税方法3つ
ここからは、ホームページ作成時にできる節税方法を3つ紹介します。
- 経費計上を最大限活用する
- 少額減価償却資産の特例を利用する(法人である場合)
- 補助金や助成金を活用する
1. 経費計上を最大限活用する
ホームページの作成費用は、可能な限り経費計上することで税負担を軽減できます。企業PRや集客を目的とした一般的なホームページは「広告宣伝費」として計上でき、制作を外部に委託した場合は「外注費」で処理することも可能です。
ドメイン費用やサーバー代は「通信費」で、軽微な修正作業は「修繕費」に振り分けられます。ECサイトや予約システム付きのサイトは、長期間にわたって使用するため「ソフトウェア」として資産計上し、減価償却が必要となる場合があります。
ホームページの目的や内容を明確にし、正しい勘定科目で計上することが重要です。
2. 少額減価償却資産の特例を利用する(法人である場合)
ホームページ制作費が10万円以上30万円未満の場合、中小企業向けの「少額減価償却資産の特例」を活用することで、一括で経費計上が可能です。通常は一定金額を資産計上し、5年間の減価償却が必要ですが、特例を利用することで、購入年度に全額経費として計上できるため、節税効果が高くなります。
ただし、特例を適用できるのは資本金1億円以下の法人に限られ、年間合計300万円までの上限があるため注意しましょう。30万円以上のホームページ制作費は対象外となるため、減価償却を行う必要があります。適用条件を満たしているかを確認し、正しく計上しましょう。
3. 補助金や助成金を活用する
ホームページ制作費の負担を軽減するため、補助金や助成金を活用する方法もあります。広告宣伝や販促を目的とする場合は「小規模事業者持続化補助金」が利用可能です。ECサイトや予約システムなどの機能を含む場合は「IT導入補助金」が適用される可能性があります。
補助金は補助対象となる経費が細かく定められているため、ホームページ制作のどの部分が補助対象になるのかを確認する必要があります。
ホームページ作成に活用できる補助金2つ
ここからは、ホームページ作成に活用できる補助金を2つ紹介します。
- 小規模事業者持続化補助金
- IT導入補助金
1. 小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、販路拡大や売上向上を目的とした取り組みを支援する補助金であり、ホームページの作成・リニューアルにも活用できます。事業のPRや販促活動を目的としたホームページの新規作成・改修を行う小規模事業者が対象です。
申請額の25%(上限50万円)が補助され、ホームページ作成費用が50万円である場合、12万5,000円の補助を受け取れます。特に、起業直後で資金に余裕がない方や、個人事業主・フリーランスにとって、大きな支援となります。
小規模事業者持続化補助金の詳しい詳細は、以下の記事で詳しく解説しているため参考にしてください。
2. IT導入補助金
IT導入補助金は、業務効率化や生産性向上を目的としたITツールの導入を支援する補助金です。ホームページ制作のうち、業務に関わる機能を含むものが対象です。
ITツール(ECサイト、予約システム、顧客管理システムなど)を導入する事業者が申請対象となります。補助上限額は、導入するITツールの種類により異なりますが50万円~450万円です。
まとめ
ホームページ作成費用の勘定科目は、広告宣伝費が一般的です。ただし、場合によっては外注費、通信費、ソフトウェア(資産計上)など複数の選択肢があり、適切に仕分けする必要があります。
比較ビズには、全国の優秀な会計士や税理士が在籍しており一括見積が可能です。税理士や会計士に依頼することで、最新の税務基準に沿った適切な科目を選定でき、税務リスクを回避できます。比較ビズの利用は完全無料であるため、まずは相談から始めてみてください。
よくある質問とその回答
岐阜県出身。上場会社の経理に勤務する傍ら、竹中啓倫税理士事務所の代表を務める。M&Aなどの事業再編を得意とし、セミナーや研修会講師にも数多くあたるほか、医療分野にも造詣が深く、自ら心理カウンセラーとして、心の悩みにも答えている。税理士会の会務では、名古屋税理士協同組合理事を務める。
固定資産になるのか経費処理できるのか、判断は、第一には金額基準になります。10万円以上の場合、固定資産計上の必要があります。
もう一つのポイントとしては、ホームページの命が1年、つまり1年以内に更新される場合は使用可能期間が1年未満ということで、固定資産に計上することはできません。
この2つのポイントをクリアできない場合は、経費処理になります。1年基準ですが、1年以上更新されないのであれば、長期前払費用等で計上し、一括の経費計上はできないでしょう。
また、WebシステムやECサイトのようにソフトウェア機能を有したホームページの場合は、無形固定資産として会計処理をしなければなりません。もっとも、10万円未満の場合は、消耗品費等、全額費用計上が可能になります。
比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。
もしも今現在、
- どの税理士に依頼したらいいかわからない
- 業界知識や実績が豊富な税理士に依頼したい
- 費用相場がわからず適正価格か不安
上記のようなお困りがありましたら、比較ビズへお気軽にご相談ください。比較ビズでは、複数の税理士・公認会計士に一括で見積もりができ、相場感や各社の特色を把握したうえで業者を選定できます。見積もりしたからといって、必ずしも契約する必要はありません。まずはお気軽にご利用ください。
顧問税理士に関連する記事
-
2025年02月27日顧問税理士ホームページ作成の勘定科目を分かりやすく紹介!経費計上の注意点3つや節税方 …
-
2025年02月17日顧問税理士格安税理士に依頼しても大丈夫?費用相場やメリットとデメリットも解説
-
2024年09月17日顧問税理士会社設立にかかる費用の仕訳方法は?考えられる経費と勘定科目を解説
-
2024年09月13日顧問税理士内装工事の耐用年数は?国税庁の年数表からよくある項目ピックアップ解説
-
2024年01月23日顧問税理士【保存版】税理士に抱く12の不満!解決法といい税理士の選び方
-
2024年01月17日顧問税理士税理士の種類には何がある?それぞれのメリット・デメリットを解説!